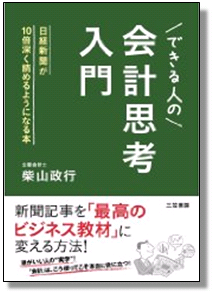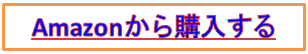できる人の会計思考入門
第1章 頭の中に、「バランスシート」をつくる!
日経新聞がどんどん深く読めるようになる!
経済取引は、この「3パターン」しかない!
会計の基本1文型?資産が増えたケース
会計の基本2文型?資産が減ったケース
会計の基本3文型?「現金を支払って、設備を購入した」ケース
たとえば、GMの破綻を会計的に考えてみると
そもそも、「会計の役割」って何?
会計の「暗黙の了解」と「最優先課題」
なぜ、破綻した会社を「公的資金」で救うの?
まずは「これだけ」!ニュースによく出る会計用語ベスト10
第2章 会計的に考えると世の中はこんなに面白い!
学校では教わらない「経済ニュース」の読み方
「個人消費」に注目すると、断然面白くなる!
「衣食住余」?経済政策を見るときのポイント
たとえば、「定額給付金」の狙いは何だった?
「在庫が増えて困っている」 このニュースから何かわかる?
「会計は、経済に、経済は、政治に勝てない」
「政治不信→消費不振→経済悪化」のスパイラル
「財政政策」と「金融政策」に注目!
「政治を厳しくチェックする目」を持とう
景気の良し悪しを測る2つの「ものさし」
経済を「お風呂の湯」にたとえてみると?
この「グラフ」を見て、何か気づきますか?
お金はどこからやってくるのか?
日銀は毎月5,000億円を供給している!?
「お金が余る」と、世の中はどうなるか
「インフレ」はこうやって起こる
日銀の「金利」の上げ下げがなぜ重要か?
第3章 時事問題を極上の経済ドラマに変える!
できる人は、「経済ニュース」をこう読んでいる!
経済ニュースを「知識貯金」に変える!
「マクロ」「ミドル」「ミクロ」の3つに分類する
「マクロ」経済ニュースの読み方?半年後に何か起こるか?
「ミドル」経済ニュースの読み方?ちょっと先の未来を予測
「ミクロ」経済ニュースの読み方?教養や法律知識を高める
日経新聞の「構成」はこうなっている
「財務は?」「利益は?」という視点を持て
「会計センス」を飛躍的に高める方法
「経済系記事」と「会計系記事」を分けて読む
時事問題を「マクロ視点」で料理する
たとえば「ゼロ金利政策」と出てきたら
「円高が日本経済に与える影響」をすぐ言える?
「日経平均」はなぜ重要な指標なのか?
「小さな政府」「大きな政府」って何のこと?
「ケインズ理論」をちょっと勉強してみよう
”ケインズ的”企業の不況対策とは?
第4章 こんなにすごい!「会計思考」
一仕事力を劇的に高める「数字センス」と「経営感覚」
ミドル・マクロ視点の経済ニュースを読み解く!
企業の「経営戦略」が手に取るようにわかる
ニュースの背景にある「業界特有の問題点」を見抜け
GM、フォード、トヨタの「失敗」から何かわかる?
「労働問題」にかかわるニュースには要注意
「地域経済」を活性化するキーワードとは?
「経営者」に関するニュースは、ここに注目!
「その会社ぱ”挑戦”しているか?」という視点
M&Aの記事は「シナジー」と「追加コスト」がポイント
企業の「不祥事」から何を考える?
「雇用問題」は、景気を読む重要指標
トヨタの社長が創業家から返り咲いた理由
実例 一会計ニュースの「3文型」分類法
「EDINET」を活用してみよう
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
 立替金(3級・2級商業簿記)
立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金 前払金(3級・2級商業簿記)
前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例 配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。 手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」 仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。